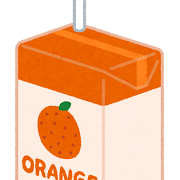6歳の男の子。
鬼ごっこ中に、「タッチしたからアウト」と言い張るお友達と、「洋服しか触ってないからセーフ」と言い張る息子さん。
どちらも自分の意見を通そうとして、周りの子を巻き込んで言い争いになり困ったことがあったそうです。
そんな時のママへの助言は、「判断を提案すること」です。
みんなに「洋服に触ったらアウトになることを知ってた?」と聞いてみます。
全員が承知していなかった場合には、「みんなで相談してルールを決めてみよう」と提案してみましょう。
都合のいいようにルールを変えたがることもあるでしょう。
でも、子どもなりに相談し、仲良く遊ぶことができるようになると思います。